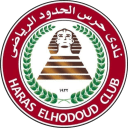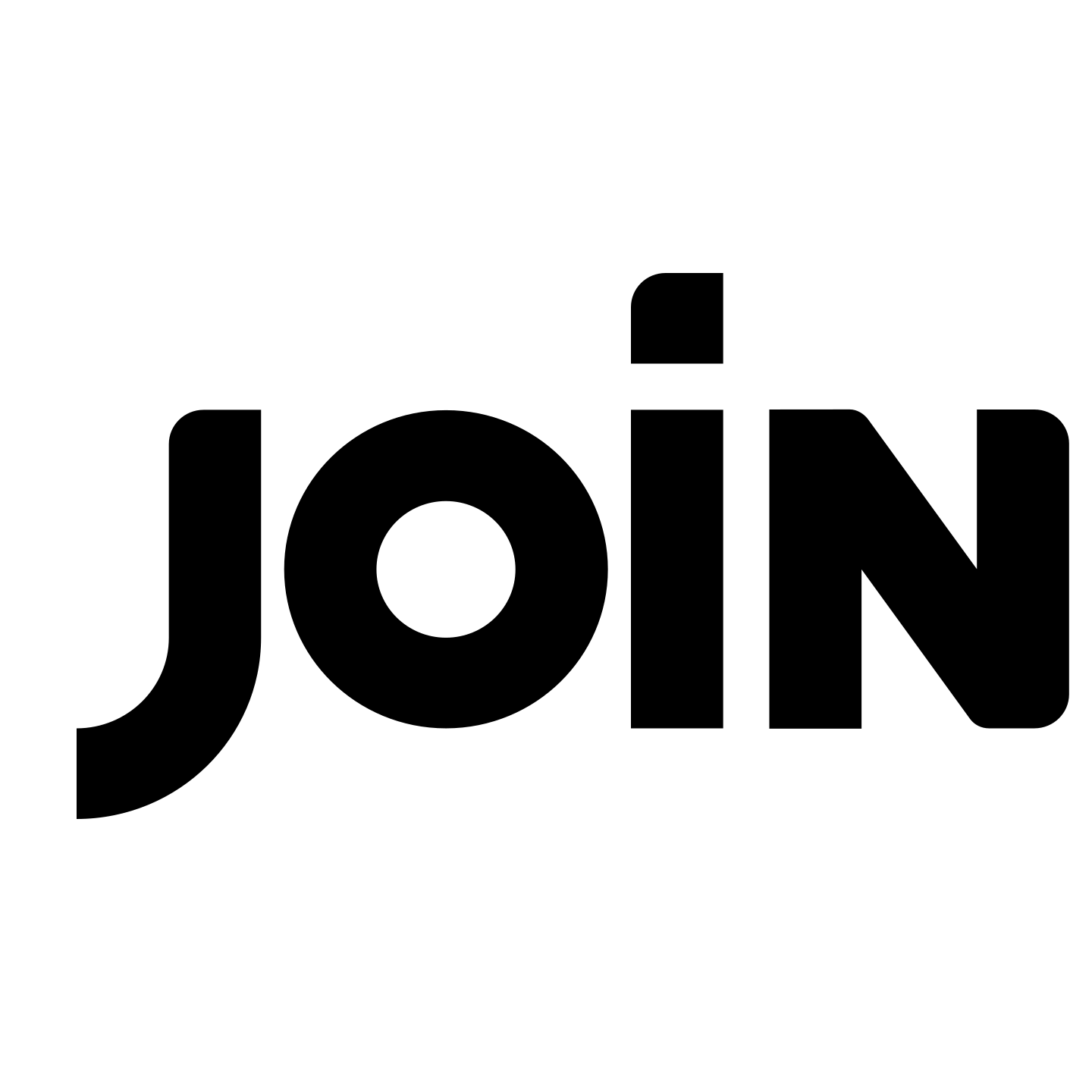九州国際大付・楠城祐介監督の野球哲学:父との葛藤から生まれた指導スタイル
九州国際大付の楠城祐介監督が語る、父との葛藤と独自の野球指導哲学。甲子園出場を目指す強豪校の日常に迫る。

九州国際大付の楠城祐介監督は、福岡県屈指の強豪校を率いる指揮官として知られています。小倉での10度、夏の甲子園出場9回という輝かしい実績を誇る同校は、平日の授業終了後、北九州市八幡東区枝光の校舎からバスで30分ほど移動し、同市若松区蜑住にある専用グラウンドで練習を行います。練習は午後2時30分ごろから始まり、シートノックや打撃練習などのルーティンワークをこなした後、自主練へと移行します。
楠城監督は、就任2年目ながら、グラウンドが2面ある環境を有効に活用しています。A班がシートノックを終えた後、B班がシートノックを行う間に、A班はもう一つのグラウンドでバッティング練習を始めるという流れです。同じ練習を繰り返すことで、選手たちに迷いを与えないようにしています。人工芝のスタジアムのような環境も素晴らしいですが、楠城監督はこの環境を気に入っており、他の高校よりも長くボールを扱う時間を確保できていると語ります。
練習は18時過ぎに終了し、グラウンド整備を済ませた後、バスで学校内の寮へと戻ります。土日の練習も午前10時から14〜15時ごろには終了し、オフシーズンは日曜を休日に充てることもあります。楠城監督の指導方針は、選手たちに「余白」を残すことです。練習をダラダラ長くやっても効果はなく、前監督のスタイルを引き継ぎ、休ませることを恐れない指導を行っています。
「前監督」とは、楠城監督の実父・楠城徹さんのことです。徹さんは1969年春の選抜大会に出場し、早稲田大学を経て、1973年ドラフト2位で太平洋(現・西武)に入団しました。捕手として活躍し、1980年に引退後は、西武で九州地区担当スカウトや一軍ヘッド兼バッテリーコーチ、スカウト部長などを歴任しました。2004年オフに30年在籍した西武を退団し、翌2005年から2012年まで楽天の編成部長やスカウト部長を務めました。
楠城監督は、父との葛藤の中で独自の野球哲学を築き上げました。父から「恥ずかしくないですか?」と問い続けられた日々が、現在の指導スタイルに大きく影響を与えています。選手たちに余白を残すことで、彼らの自主性を引き出し、甲子園出場を目指す強豪校としての地位を確立しています。