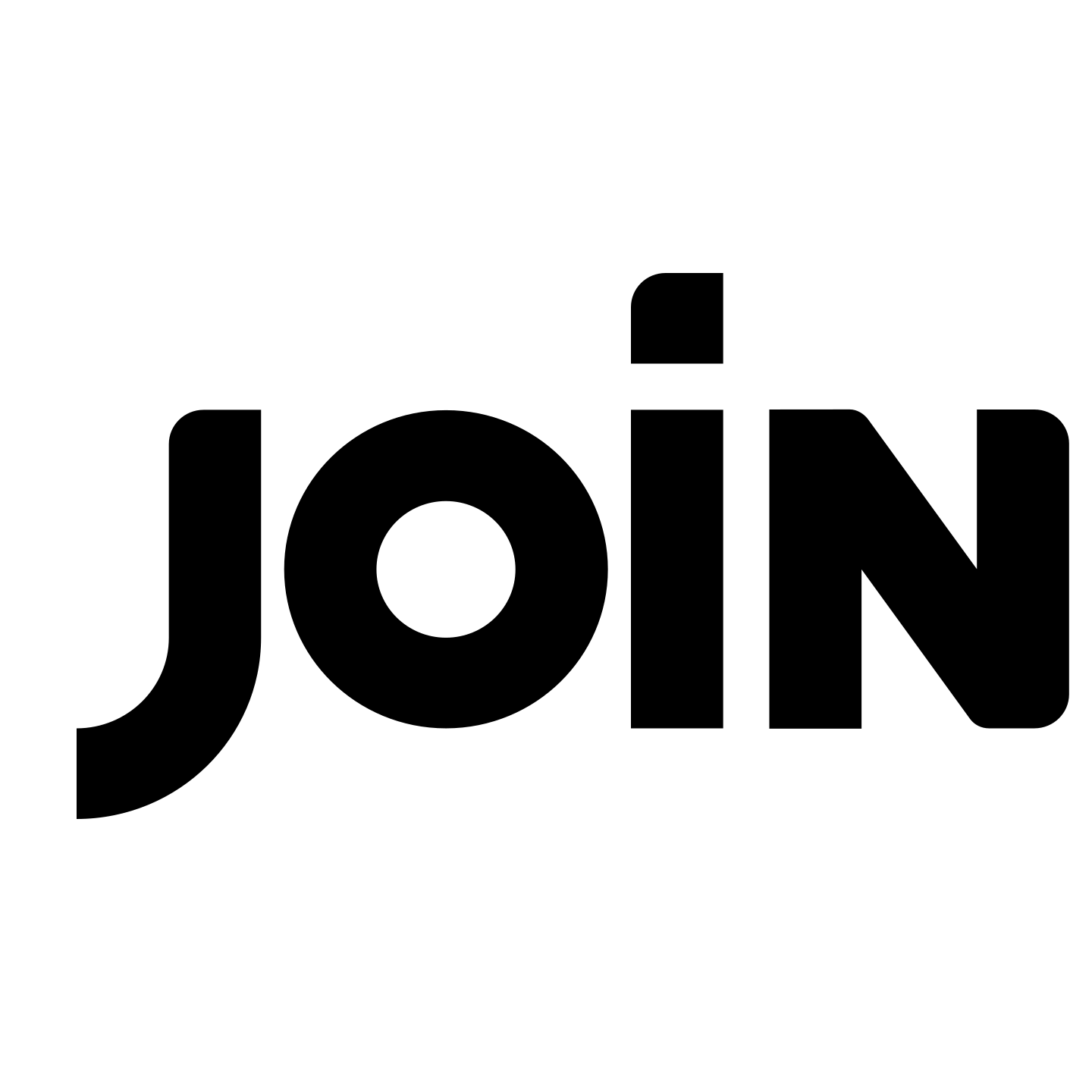大相撲の歴史と初代両国国技館の物語
1909年に開館した初代両国国技館の歴史と大相撲の深い関わりを探る。名建築家辰野金吾と葛西萬司が設計したこの建物は、大相撲初の屋内常設会場として知られています。

初代両国国技館の誕生
1909年、大相撲初の屋内常設会場として、東京・両国に初代国技館が完成しました。この建物は、辰野金吾とその教え子である葛西萬司によって設計され、ドーム型の天井を鉄の骨組みで支える構造が特徴でした。その独特の形状から「大鉄傘」の愛称で親しまれました。
短い栄光と悲劇
しかし、完成からわずか8年後の1917年、火災により焼失してしまいます。その後、再建された国技館は、関東大震災や太平洋戦争での空襲により、再び火災に遭いました。戦後は連合国軍総司令部(GHQ)に接収され、蔵前国技館を経て、1985年に現在の両国国技館が建設されました。
大相撲と国技館の絆
初代国技館は、大相撲の歴史において重要な役割を果たしました。屋内常設会場として、天候に左右されない環境で試合が行えるようになり、大相撲の人気をさらに高めることになりました。現在の両国国技館も、その伝統を受け継ぎ、大相撲の聖地として多くのファンに愛されています。
建築家の偉業
辰野金吾と葛西萬司は、東京駅や日本銀行本店など、数々の名建築を手掛けたことで知られています。初代国技館の設計も、彼らの技術と情熱が詰まった作品の一つです。その建築スタイルは、当時の技術の限界を超えるものであり、現在でも高く評価されています。
今に続く遺産
初代国技館は短命でしたが、その影響は今も続いています。大相撲の伝統と歴史を伝える重要な場所として、両国国技館は多くの人々に愛され続けています。